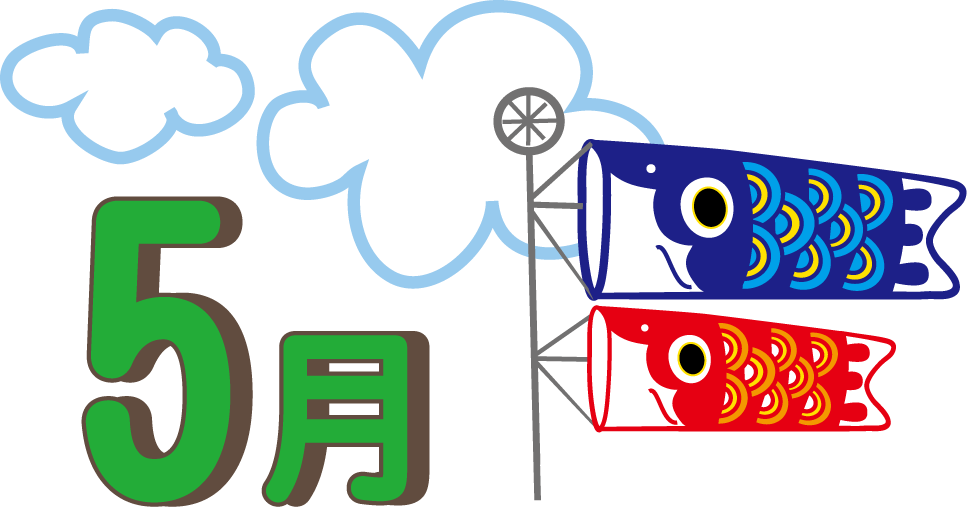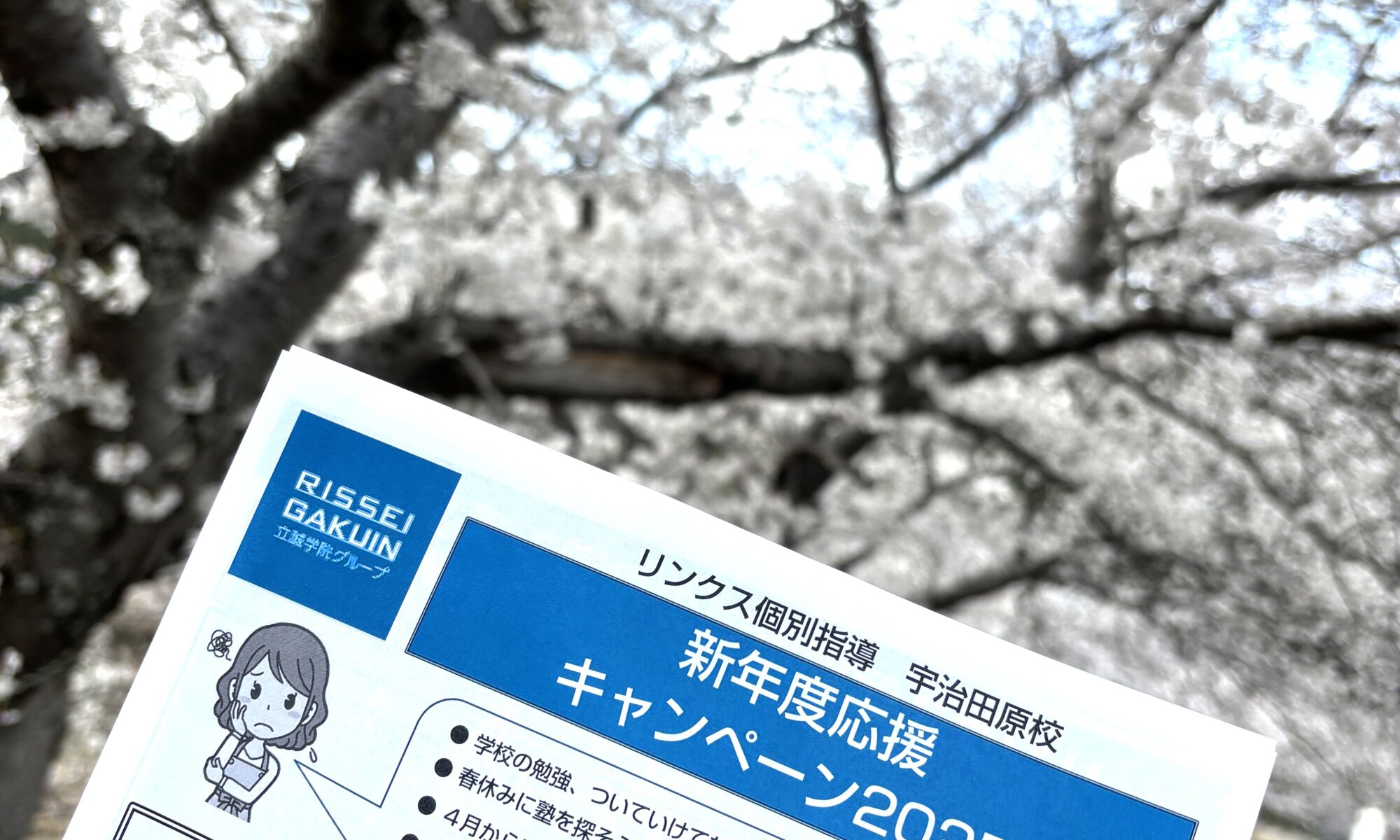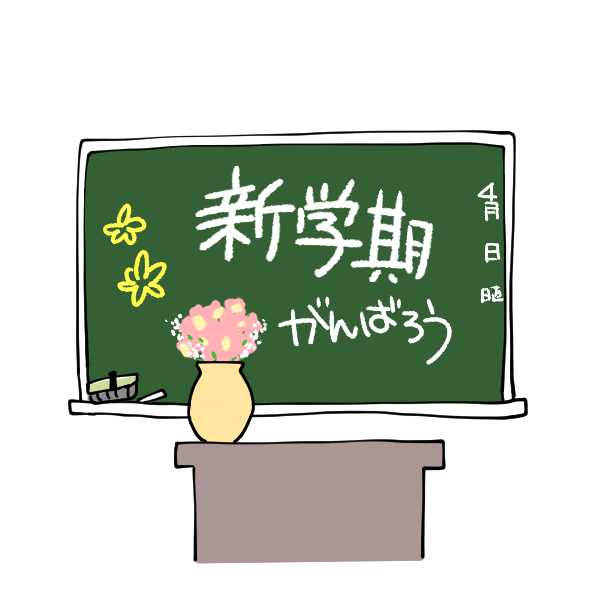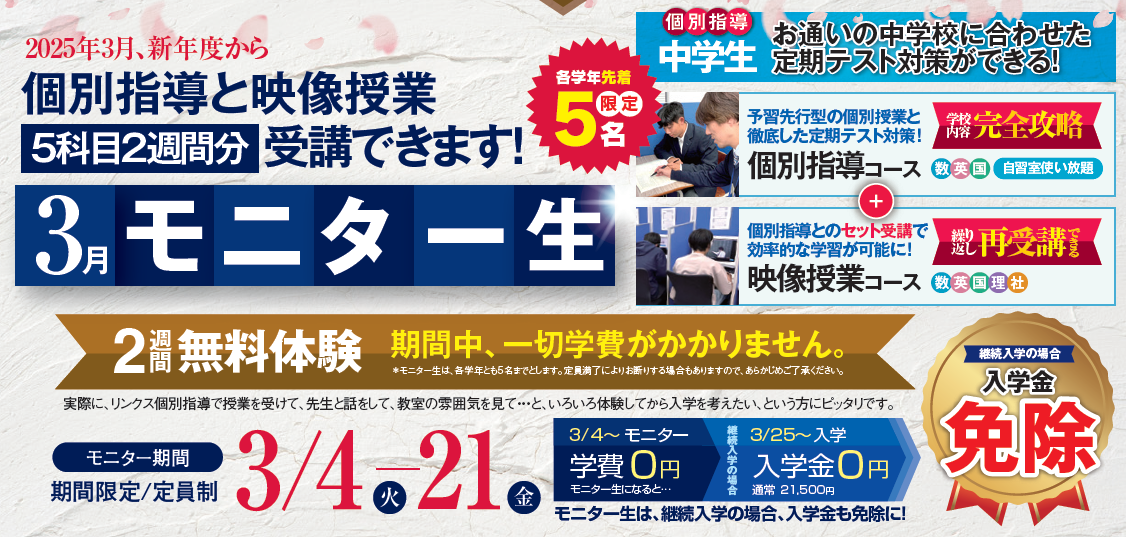こんにちは!京都府城陽市にあります、リンクス個別指導城陽校の栗本です。
GWも終わり、学校生活が本格的に始まっていきますね。今年は、飛び石での連休だったこともあり、あまり休んだ感がないかもですね。。。
さて、GW明けて中間テストが行われる学校は気付けばテストまでもう少し。。。
「うちの中学校は中6月までテストないしラッキー」と思っているお子様はピンチです!
5月にテストがないということは。。。
①4月~6月までの約3か月分の範囲が出題される(=範囲が広い。。。)
②副教科も含めて3日間でテストが行われる(=やることも多い。。。)
③1学期の通知表が1回のテストで決まってしまう(=失敗できない。。。)
まだテストまで1カ月以上あるし、大丈夫かと思いきや、よく考えるといつものテスト1週間前から頑張ればいいでは間に合いません。。。
普段から、予習⇒学校の授業⇒復習のサイクルをしっかりと取り組んでいくことが大切です。
「でも、自分でやるのは無理だ」「うちの子毎日スマホばっかり。。」という方は何か勉強する環境を作ることから始めてみましょう。
リンクス個別指導城陽校は、普段の授業は学校の予習を進めます。そして、テスト範囲が終わり次第、復習を生徒ごとに行っていきます。
一度、テストまでの勉強のサイクルを一緒に作ってみませんか?
「やってみようかな」と思った時がチャンス!
リンクス個別指導城陽校を体験してみてください!!
★HPブログ
https://kobetsu.links-edu.jp/blog/
https://www.instagram.com/linksgroup_edu/
https://ja-jp.facebook.com/linksgroup.edu/
★立誠学院グループHP
https://www.rissei-gakuin.com/
☆Google口コミもよろしくお願いします!☆
https://g.page/r/CYYeK5mD6bzrEBM/review