こんにちは、加茂駅前校の津村です。
長かった夏休みも終了し、本日から加茂駅前校近隣の小中学校では2学期が始まりました。
夏期講習期間中はただただ授業に邁進したり、中3生はサマートライアルでシビアな結果に向き合ったりと、充実した夏を過ごすことが出来たかと思います。
夏休みが明けたら明けたで、泉川中学校は定期テスト3週間前という余裕のない状態で、なかなか焦ってしまう状態ですが……汗
ということでコマーシャル
ポスティングチラシ(テス攻)ver,2m
毎テスト前おなじみの定期テスト対策。
今回は9/13(土)・14(日)の2日間で実施です。
さらに、2年生に朗報!
中2 2学期中間数学特講チラシいろんな言語・解き方・応用問題と難しすぎるポイントが多すぎる1次関数。
夏休みを挟んでのテストは非常に厄介です。
ということで、特別講座を実施します。
↓↓↓↓↓お問い合わせはコチラまで↓↓↓↓↓
https://kobetsu.links-edu.jp/contact/index.php?type=question
さて、話を戻しまして、昨日まで続いた夏休みですが、生徒たちの天敵ともいえるのが夏休みの宿題。
早々に片づけてしまった子から、お盆あたりまで手を付けずに寝不足になる子まで様々だったかと思います。
そんな夏休み課題の中でも特に厄介と言われる「作文系」の課題についてですが、最近はAIの発達により、内容をAIに考えてもらって、それを写して完成させるという子が中高生を中心に増えてきました。
確かにAIをうまく活用すると、わからない英文を翻訳したり、数学の解き方を調べたり、歴史の要点を整理したりと、AIはまるで「家庭教師」のような存在になりつつあります。
しかし、その便利さゆえに「どのように使えば学びに役立つのか」「依存しすぎると何が起こるのか」といった課題も浮かび上がっています。
1. 宿題にAIを使うメリット
AIをうまく利用すれば、学習効率は大きく向上します。
-
調べ物が早い:教科書や辞書を何冊も開かなくても、要点がすぐにまとまる。
-
解説がわかりやすい:数式の途中計算や英文の文法構造など、手順を追って理解できる。
-
繰り返し質問できる:恥ずかしさを感じずに、納得いくまで疑問を解消できる。
これらは、特に自宅学習で誰にも聞けない場面において、大きな助けになります。この点は、インターネット環境さえ整えばどれだけ田舎に住んでいようとも都会の子と同じように学習できる助けとなります。
2. 注意すべき点
一方で、AIに頼りすぎることにはリスクもあります。
-
答えだけを写してしまう:学びが身につかず、テストで再現できない。
-
誤情報のリスク:AIは正しいように見える誤答を返すこともある。
-
思考力の低下:自分で考える過程を飛ばしてしまう危険がある。
当然ですが、宿題は単なる「提出物」ではなく、「理解を深める練習の場」です。その目的を忘れると、かえって成績が伸び悩むことにつながります。
3. AI活用の正しいアプローチ
では、実際にAIを宿題に取り入れるときには、どのような形が望ましいでしょうか?実際に使う際は次のような使い方が望ましいでしょう。
-
ヒントや解き方を聞く:答えを丸写しするのではなく、途中の考え方を参考にする。
-
自分の理解を確認する:AIの説明を読んだあと、自分の言葉で要点をまとめる。
-
比較して検証する:教科書や他の資料と照らし合わせ、正確さを確かめる。
こうした使い方なら、AIは「ズルの道具」ではなく「学びを深めるツール」として機能します。
4. 教育現場のこれから
学校でも、AIの使用をどう位置づけるかが議論されています。「禁止すべき」ではなく「どう使えば教育にプラスになるか」を考える時代に入ったと言えるでしょう。将来的には、宿題の指示そのものが「AIを活用して調べ、考察をまとめなさい」という形に変わっていく可能性もあります。
◆ まとめ
AIは、中高生にとって宿題を「効率的に進める味方」にも「考える力を奪う存在」にもなり得ます。大切なのは、AIを“答えをくれる存在”ではなく、“学びをサポートする存在”として位置づけることです。宿題を通じて培うべきは「自ら考え、表現する力」であり、AIはその力を伸ばすための道具として活用していくべきでしょう。
さて、ここまでのブログ内容ですが、
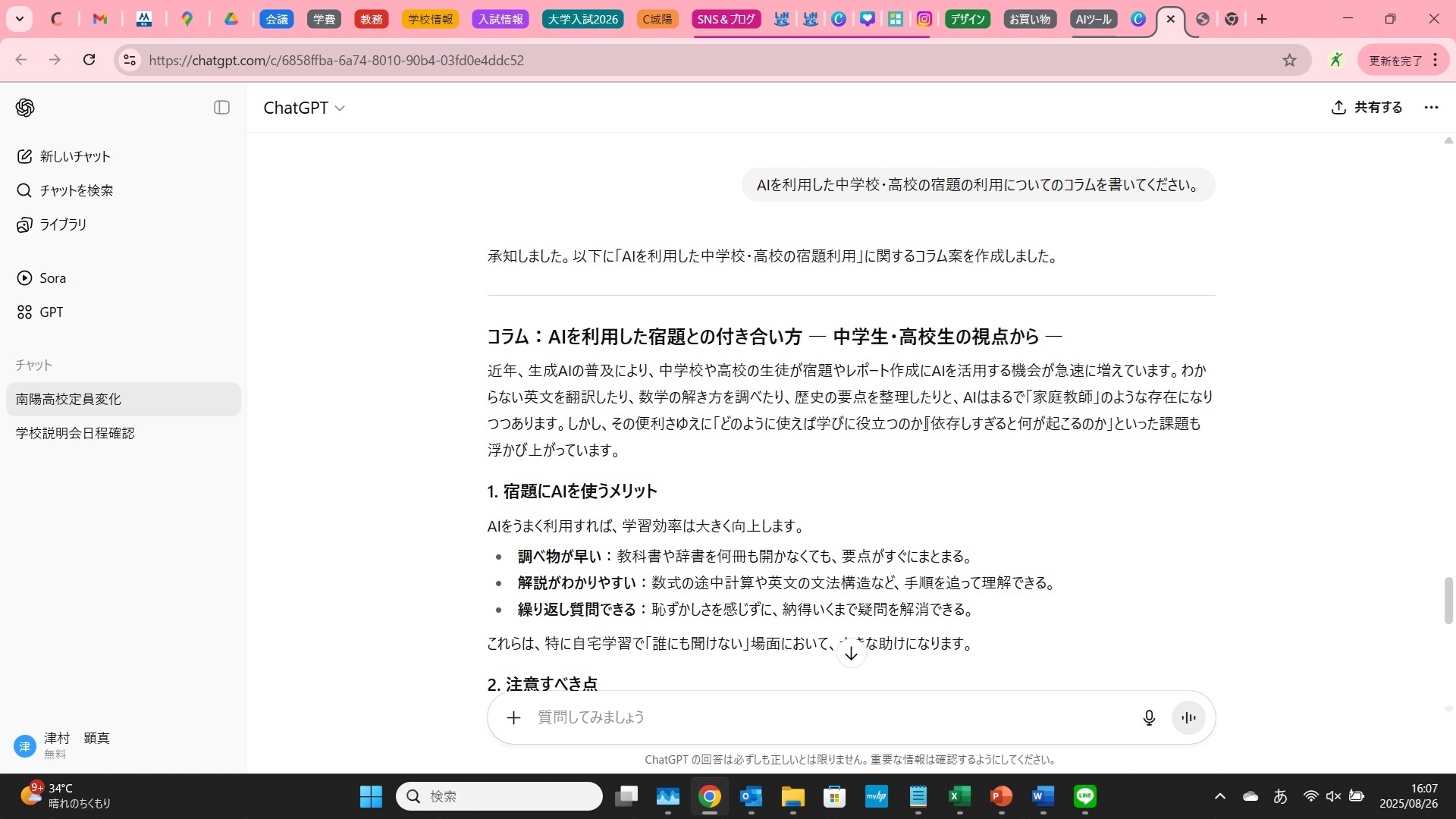
導入部以外の文章作成作業をAI【ChatGPT-5】を用いて作成してみました(笑)
確かにこれは便利です!
特に原稿用紙に書かなくてよいブログや手紙の執筆においては圧倒的な時間短縮になります。
ただ、実際の学習に導入していく事については、まだまだ社会が受け入れる体制になっていないようにも感じます。
そもそも、各調査機関においても日本人は諸外国に比べて「AIに対して期待よりも慎重な意見が多い」 という特徴がはっきり出ています。その事から、AI利用については『ズルをしている』という意識が出やすい傾向にあります。そのような環境下で『AIに手伝ってもらった』と声を上げると、『答えを写した』と同義にとらえられてしまい、正しく使う意識が生徒やご家庭にあったとしても、無為なやり直しをする羽目になったり減点されて成績に響いたりします。
ですが、AIを用いた事によって浮いた時間で、新しく別の事をチャレンジする時間に充てられるなど、メリットもたくさんあります。そのような時間を『ズルをした』というレッテルを貼ることで大人たちが潰してしまうというのも、またもったいない事ではないかと感じます。ただ、この『ズル』と『活用』の線引きが非常に難しく、このあたりを世の大人たちがまだつかみ切れていないというのが現状と言えるのではないでしょうか?
AIに限らず、子供たちの勉強というのはどこまでを泥臭く・どこまでを効率的に行うべきかを日々模索していく必要があります。
『教育者』と言われる以上、その線引きを日々模索しながら生きていきたいと思う今日この頃です。
★HPブログ
https://kobetsu.links-edu.jp/blog/
★Instagram
https://www.instagram.com/linksgroup_edu/
★立誠学院グループHP
https://www.rissei-gakuin.com/
☆Google口コミもよろしくお願いします!☆
https://g.page/r/CW8_BX1ruLiKEB0/review





